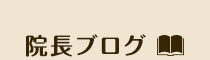痛みはなぜ起こるのか?痛みの種類について

痛みは人にとって必要か?
誰にとっても不快な『痛み』。本来必要なものかどうかを改めて考えてみましょう。
痛みという警報装置
誰にでも一度は、ドアに指を挟んだり、画鋲を踏んだりして『痛い』と感じた経験があると思います。
ご存知の通り、痛みはとても不快でいやな感覚です。誰しも、『痛みなんてなければいいのに』と思ったことがあるでしょう。しかし、痛みは本当に不必要なものなのでしょうか?
本来、痛みには警告信号としての役割があります。そのため、身体が危険に冒されたとき、人は痛みがあるからこそ危険を察知し、危険から逃れることができます。実際に先天的に痛みを感じない先天性無痛症という病気がありますが、この病気の人は痛みを感じないため怪我をしていても気がつきません。そのため、手足が壊死(細胞が死滅し、部分的に腐ってしまう状態)を起こして致命的な障害を負うこともあります。この意味で、痛みは身体を守るために大切なシステムなのです。
一方、ドアに指を挟んだ時など、痛みがあると人はその痛みから逃れようと無意識に身体が反応します。このような現象は逃避反射と呼ばれ、ナメクジウオのような下等動物でも備わっている大切な反応です。痛みで危険を知らせると同時に、無意識にその危険から逃れようとする機構が備わっているのです。
ただし、警告信号としての役割があるのは急性通だけであり、慢性痛には警告信号としての役割はあまりありません。痛みは警告信号ですが、むやみに長く存在する必要はないのです。『痛みが出現したら原因を見つけ、回避する。警告信号の役割が終われば、痛みを止める』これが、痛み治療における鉄則です。
- 痛み(急性痛)は警告信号としての役割をもつ
- 痛みにより危険から逃れようとする機能が備わっている
- 原因が排除された後の痛み(慢性痛)は不要である
生活で感じる痛みの疑問/痛みと天気
雨が降る前はなぜ痛むのか?
痛みと天気の関係について理解しましょう。
○痛みで天気予報!?
『天気が悪くなると、なんとなく調子も悪い』という話はどこかで聞いたことがあるでしょう。特に、長い間痛みにさらされた古傷があると、その傾向は強く現れます。実際に患者さんのお話を聞いていると、雨が降っている時より、降る前の方が痛い人が多いようです。これはなぜなのでしょうか?
低気圧が近づくと、気圧は徐々に下がり雨が降ります。気圧が下がると、耳の中にあるセンサー(内耳)がそれを感知し、視床下部を通じて交感神経活動が亢進します。交感神経活動が亢進すると、神経末端からノルアドレナリン(NA)と呼ばれる物質が血中に放出され、痛みを感じる神経や一部の侵害受容器を刺激します。
また、NAは血管を収縮させたり、血液中のマクロファージや肥満細胞を活性化させてヒスタミンやTNFαと呼ばれる物質を放出し、痛みを感じる神経を刺激します。さらに、副腎髄質にも働きかけてアドレナリンを分泌し、同様に痛みを感じる神経を刺激します。
普通の状態では、気圧が下って痛みを伝える神経や受容器が刺激されたとしても、痛みを感じることはほとんどありません。しかし、あらかじめ神経損傷や炎症などが存在すると、侵害受容器やDRGなどに正常時では認められなかった交感神経に反応する受容体が新たに出現するため、気圧の変化でも痛みを感じるようになります。そのため、古傷を抱えた人は、気圧の変化に敏感になり、天気予報ができるのです。
- 天気が悪くなる(気圧が下がる)と痛みは悪化する
- 気圧の低下は内耳を刺激し、交感神経の活動を高める
- ノルアドレナリンが分泌されると、痛みを感じる神経を刺激する
心因性疼痛とは?
心因性疼痛について理解しましょう
○心の叫び声
痛みの中には明らかな原因がないにも関わらず痛みが存在するもの、また痛みの原因があるとしてもその原因では訴てる痛みを説明することができない場合などがあります。このよう場合、痛みをどのように理解すればいいでしょうか?
組織の損傷に伴う侵害受容性慢性疼痛や、神経の損傷に伴う神経障害性疼痛のように、ここまで痛みには必ず原因があるかのように説明してきましたが、心因的な問題がある場合、明確な損傷や炎症がないにもかかわらず痛みを訴えることがあります。これを心因性疼痛と呼んでいます。
しかし、痛みが慢性的にある場合、どんな人でも少なからずストレスなどの心因的トラブルを抱えています。うつなどの精神症状を訴えていることが多く、それをもって心因性疼痛ととらえがちです。心因性疼痛は『その痛みが心因的なものが心因的なものでしか説明することができない状態』を指し、痛みの原因が明確にあり、それに伴い心因的な問題が出現したものは除外されます。そのため、ストレスの有無や精神症状の有無だけで心因性疼痛と判断することはできません。
心因性疼痛の代表的なものは、身体表現性障害の中の疼痛性障害だけです。痛みを説明するのに十分な身体的異常がないにもかかわらず、重篤な痛みが続くもので、全身の痛みの他、吐き気や下痢などの胃腸症状、ふらつきや脱力などの神経症状を呈するのが特徴です。もちろん、これらの症状は意図的に作られたものではないことも理解しておかなくてはいけません。
- 心因性疼痛は、心因的な問題意以外に痛みを説明できないものをさす
- 痛みに伴ってうつなどの精神症状が存在ものとは区別が必要である。
身体を動かして痛みをとる!
理学療法について理解しましょう。
○痛くても身体を動かすことは大切!
痛みが強いときは、動きたくないものです。この反応は、生体の防御反応として正常な反応ですが、慢性痛のように痛みのために動かない時間が長時間続くと、状況は一変します。一般的に長時間筋肉を動かさないと筋力は低下し、廃用性萎縮と呼ばれる状態になります。さらに筋肉を動かさなければ関節拘縮になります。これらが生じると、動きが制限されるのはもちろんのこと、廃用性萎縮を起こした筋力や関節拘縮が起こった関節の動きを他の筋肉や部位が代償しようとし、負担をかけることで二次的な痛みが出現します。
このように、筋肉を長時間動かさないことで新たな痛みを発生させる可能性があることから、筋力を増強させる運動や関節を動かすような運動を指導します。これらは、筋力トレーニングや関節可動域訓練と呼ばれ、痛みのリハビリテーションとしては一般的な方法です。
一方、歩行や体操などの軽い運動は、廃用性萎縮や関節拘縮を予防するだけでなく、その運動自体が鎮痛を起こす役割を持っています。一般的に、軽度の有酸素運動を行うと、脳内から内因性のオピオイド物質が放出されることが知られていることから、痛みがある程度あっても身体を動かすことは大切であると考えられています。ただし、運動の量や強度は、痛みの強さや疾患の種類により異なるため、運動を行う際は専門家の指示を受けることが好ましいと思われます。いずれにせよ、痛みが出た場合は、身体を動かすことが大切です。
- 関節可動域訓練は、萎縮や拘縮だけでなく、痛みの予防にもなる
- 軽度な有酸素運動は、脳内からオピオイド物質を誘発することで、痛みを抑制する